【行政書士試験】商法・会社法を捨てるのはアリか?

はじめに結論
結論からいうと、アリだと思います。
なぜなら私自身、商法・会社法0点でも合格してるからです。
他にも商法・会社法0点で合格した人を何人か知っています。
商法・会社法はコスパ・タイパ悪すぎ
まずは、行政書士試験の配点マップを見ていきましょう。
敵を倒すには敵を熟知する必要がありますからね。
| 科目 | 択一 | 多肢選択 | 記述 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎法学 | 8 | 8 | ||
| 憲法 | 20 | 8 | 28 | |
| 行政法 | 76 | 16 | 20 | 112 |
| 民法 | 36 | 40 | 76 | |
| 商法会社法 | 20 | 20 | ||
| 一般知識 | 56 | 56 | ||
| 合計 | 300 |
誰もが知っての通り、行政法、民法が2トップです。
普通は、配点の大きい 行政法・民法・憲法 を重点的に勉強して行くと思いますが、大抵そこで手一杯になって、どうしても商法・会社法まで手が回らない!となるのが普通です。
私の場合、商法・会社法は、模試では適当に解いても5問中2~3問当てていましたが、かなりやり込んだあとでも正当数は2~3問と変わりませんでした。
つまり、なんとなく雰囲気で2~3問当てていたのが、確信的に2~3問取れるようになったというだけで、結果的に何も変わらなかったのです。
しかも本試験では0点。時間返せ!という気持ちになりました。
それでも合格したのは、行政法、民法をやり込んだからだと思います。何と言っても、行政法、民法には大逆転チャンスの記述がありますからね!徹底的にやり込むべきと思います。
商法・会社法を捨てるという潔さ
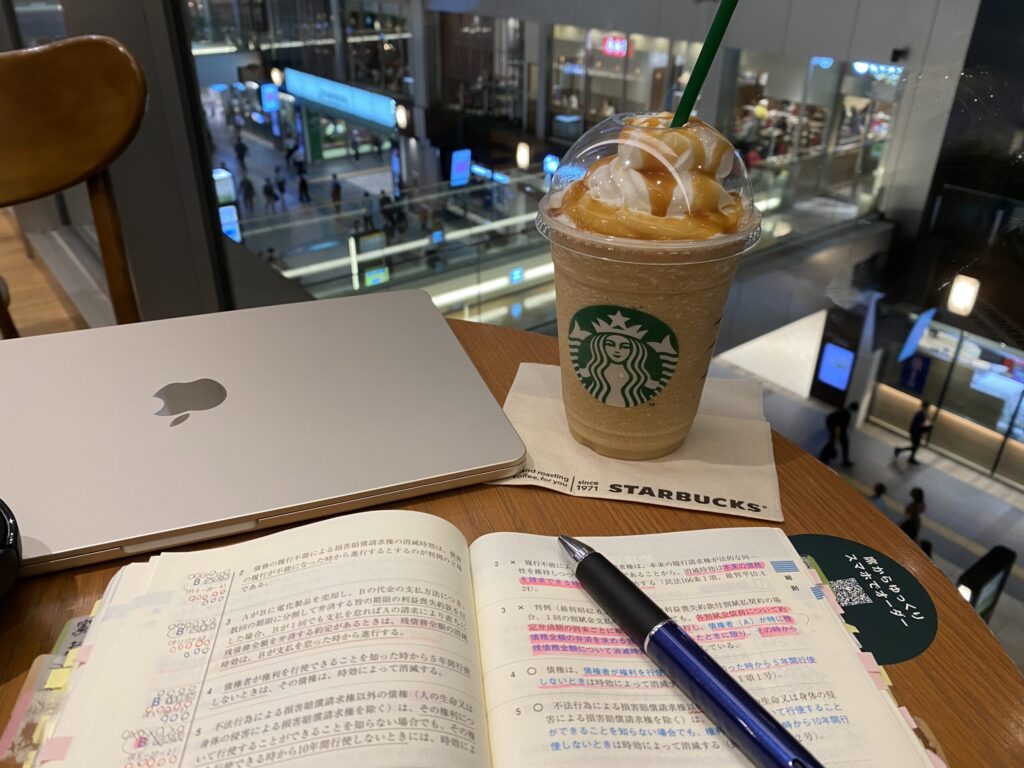
捨てるかどうかは、実際に勉強してみなければ分からないところがあるので、最初から「捨てる!」という判断は早とちりになるかもしれません。
人によっては、商法・会社法が楽しい!簡単!自分に合ってる!と思うかもしれないし、判断するのは少しかじってからの方が良いでしょう。
まずはなんといっても、行政法、民法、そして憲法です。
この3つが安定して高得点を取れるようになってきたら、商法・会社法にリソースを割くのはぜんぜん有効だと思います。
私なりの目安として、模試で以下の点数を安定して取れるようであれば、商法・会社法にがっちりリソースを割いても良いのかなと。
- 憲法 :4/5問
- 行政法:17/19問
- 民法 :7/9問
まとめ
あくまでも個人的な意見として参考にして頂けたらと思います。
商法会社法は範囲がめちゃくちゃ広く、出ると言われている設立、組織、株式等に絞った勉強をしても、私はどうしても理解できず、当然楽しいとも思えず、苦痛でした。問題文の言い回しだけで拒絶反応を示すぐらいでした。
それでもやり込んで、少しは理解してきたと思って模試やっても全然点数は伸びませんでした。しかも本試験では0点(涙)
仮に、商法会社法をやり込んで満点取ったとしても20点。そんなにやり込んでなくても2、3問は取れたりするものです(8〜12点)。つまり、積み上げられるのはせいぜい2、3問(8〜12点)ぐらいなのです。はっきり言って、コスパ、タイパ悪すぎ!
まずは行政法、民法、憲法、そして足切り回避で諸法令、最後に商法会社法で良いと思います。
ちなみに私が使用した商法・会社法の参考書は以下です。いろいろみた中でも伊藤塾のこれが一番簡潔にまとまっていて分かりやすかったです。良かったら参考にしてみて下さい。
他にも行政試験対策の記事を公開していますので、以下から気になるキーワードをクリックしてみて下さい。
